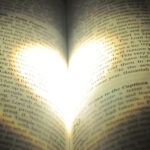研究計画書の書き方講座──合格を掴むテーマ設定から徹底的なマンツーマン添削まで
研究計画書は、大学院の合否に大きく左右するものです。
大学院の試験官は研究書から、「この学生は研究者としての基本的な資質を備えているか」「独自の視点から研究を行える論理的思考力を持っているか」「心理学という学問領域を理解しているか」という極めて本質的な能力を見極めます。Meg心理師予備校では、この生命線とも言える研究計画書の作成を、テーマ選定の初期段階から構成、そして完成に至るまでの詳細な添削まで、経験豊富な講師が完全マンツーマンで徹底的に支援しています。
1. 研究テーマは「自己理解の延長線」から学問的課題へ
テーマ設定は、研究計画書作成の成否を握る出発点であり、多くの受験生が最初に直面する壁です。研究とは、決して直感的ではなく、自分が心を動かされた経験や、社会の中で感じた違和感・問題意識の延長線上にあります。
たとえば、「不登校支援における親子の葛藤」「高齢者の孤独と地域コミュニティの機能」「若者のSNS依存と自己肯定感の関連」「発達特性を持つ人々の職場の適応」など、個人的な関心や原体験を深く掘り下げることが重要です。
講師は、受講生が作成した研究案を興味で終わらせず、その興味の核にあるものを学術的な言葉で言語化し、研究可能な「問い」へと精緻化させます。このプロセスこそが、独創的で説得力のあるテーマを生み出す鍵となります。
2. 構成の基本:一貫性と論理的接続の徹底
優れた研究計画書は、その構成に揺るぎない一貫性があります。一般的に、研究計画書は以下の5つの要素で構成されます。
研究背景・目的: なぜこの研究が必要なのか、その学問的・社会的意義。
仮説・課題: 研究を通じて明らかにしたいことの具体的な想定や問い。
方法(対象・手続き・尺度など): 仮説を検証するための具体的なアプローチ。
分析計画: 得られたデータをどのように処理・解釈するか。
考察・意義・限界: 研究が成功した場合に何が言え、将来的な展望は何か。
ここで何よりも大切なのは、形式を整えること以上に、「何を明らかにしたいのか」という中心的な問いが、すべての節で一貫して貫かれることです。特に、「研究背景で示した問題意識」と「それを解決・検証するための具体的な研究方法」が、論理的かつ自然に接続しているかを、講師と受講生が常に確認し合いながらブラッシュアップしていきます。この接続が甘いと、「方法論のための研究」に見えてしまい、評価が大きく下がります。
3. 先行研究の扱い方:研究の位置づけを明確に
学術的文脈において、先行研究のレビューは必須であり、あなたの研究の価値を決定づける分岐点となります。
重要なのは、「誰が何を明らかにしたか」を単に並べるだけでなく、「その結果、現在の時点で何が未解明として残されているのか」「自分の研究はその未解明な部分をどのように埋めるのか」を整理し、明確に提示することです。
Megでは、主要論文の効率的な読み方、広範な知識を得るためのレビュー論文の使い方、そして適切な引用・参照の形式(APAスタイルなど)まで を徹底的に指導します。「自分の研究が過去の膨大な研究群の中でどの位置に立つのか」を論理的に説明できる学生は、口頭試験においても「研究者としての基礎体力がある」と高く評価され、圧倒的に有利になります。
4. 書き直しを通じて文章ではなく思考を磨く
研究計画書は「一度書いて終わり」の書類ではありません。講師は、添削を単に赤字で直すのではなく、「なぜこの結論に至ったのか?」「その根拠は何か?」と問いかける対話を通じて、受講生の思考を深く掘り下げていきます。この「対話を通じた何度もにわたる改善(リライト)」の過程で、文章の表現が洗練されるだけでなく、テーマに対する受講生自身の理解と論理的な思考自体が根本的に整理され深化していきます。
AIによる添削ツールが増えている現代ですが、AIでは決して補うことのできない「思考の深まり」と「論理の飛躍の指摘」こそが、研究計画書の説得力を最大限に高める最大の要素であり、合格へと直結するカギとなります。最終的に、受講生は自信を持って自分のテーマを語れるようになり、口頭でも動じない揺るぎない論理力を身につけることができます。
作成者:Meg心理師国試予備校スタッフ
【公認心理師】新田 猪三彦(にった いさひこ)
2007年より心理学や脳科学の講座を行い、医歯薬専門予備校で受験に必要なメンタルの強化法、保育士会調査研究委員会において「保育士・保護者のコミュニケーション講座」、市民と協働によるまちづくり提案事業、産学官包括連携事業などを行っている。
九州朝日放送運営のマイベストプロ福岡でコラムの執筆にも携わり、一人でも多くの人が心が豊かに生活できるように情報を発信している。
また、部活動のメンタルトレーニング、学校を中退した学生の受験・学習支援、受験を見守る保護者の相談、資格試験合格のためのモチベーション管理、タイプ別による学習法のアドバイスなども行っている。
<略歴>
公認心理師 /ふくおか成年後見センターさくら / 福岡コミュニケーションカレッジ講師 / PMD医歯薬専門予備校心理カウンセラー / 日本心理学会認定心理士 / 日本メンタルヘルス協会認定基礎心理カウンセラー / 文部科学省所管生涯学習開発財団(神経言語プログラミング)協会認定マスタープラクティショナー / ICA(国際コーチ協会)認定コーチ / カナダSuccess Strategies・Shelle Rose Charvet認定LABプロファイリング・プラクティショナー
・メンタルゼミ